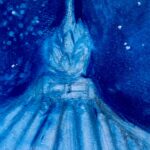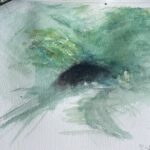《アネット》1951年
ジャコメッティの絵画は、とても不思議だ。
彼の絵を眺めていると、今、目の前のモデルを自分が描いている、そういう状況を錯覚する。
もちろんそうではないはずなのにジャコメッティの絵画は、「モデルを描いた肖像画」ではなく、
今、モデルを描いているという「事実」、あるいは「時間」を共有する媒介のような役割をしているなのではないかという気がする。
血走りながら眼をはしらせ、汗とほこりにまみれながら暗がりの部屋のなかで何十時間も拘束し、描いては消し、描いては消しながら完成など求めず格闘を続ける。そんな自分が確かにいるのだ。
これはいったいぜんたいどういうことなのだろう。
彼の強迫にかられ、ついには、私たち自身がそのモデルを見つめ、えがいている彼自身になりかわっているのか。
「作品」としてではなく
肖像画を見て、まるでモデルがそこにいるかのようだ、とかそういうことはよく思うことだ。

《真珠の耳飾りの少女》
このフェルメールの傑作も、まさしくそうだろう。
少女の空気感、今にも動きだしそうな、一瞬の時間を切り取ったかののような繊細な表現。
しかし、ジャコメッティの肖像画には、繊細なディティールも、リアルな表情も、瞳も、動きもない。
かわりにあるのは、部屋の中に人物が座っている、それを見ている、あるいは人物に見られている状況、あるいは時間、あるいは空間。
どれもこれも抽象的で、ぴんとこないが、彼の絵を見て当てはまる言葉はこれくらいしかないのだ。
絵をみている自分が、モデルを描いている気持ちになる肖像画」など、わたしは知らない。
思うに、絵画として完成させた時点で、それはそのもののようでそのものではない別の世界にすりかわているのだ。作者の考え、構成、テーマ、これをこのように描こう、そのような理性的な思考が加われば加わるほど、目の前に生きているモデルとの時間からは遠のいていく。
彼は作品という幻想のなかに生きたのではなかった。作品も、完成もない、ただ目の前に座るモデルとむきあい、格闘する時間があるだけだ。
目を凝らした先に見えるもの
ジャコメッティは、人物の頭部を描きつづせたが、頭部を見つめるうちに、その存在の神秘にひかれ、生涯にわたって、その正体を突き止めようとした。
絵のなかで、絶対に到達できないと、わかっていながらもそこに、むかって一歩ずつ、前進することを選んだ。
ジャコメッティの制作におけるモデルへの執念は凄まじいものがあるのは、彼の絵の線から見てとれる。
彼は、線を引っ掻くように、あるいは消しながら、文字通り身を削りながら描いた。
わたしは、死にもの狂いで奮闘する画家の意味を考えずにはいられない。
これは、とても忍耐のいる、命懸けとも呼べる追及行為である。
はたからみれば、それは理解しがたいことであるにちがいない。
でも、彼の絵を前にすれば、その疑問は一瞬で吹き飛ぶ。
なぜそれが大切なのか、そんなことはどうでもよくなる。
ただ、対象と向き合い、目を凝らし続けた先に捉えた名伏しがた「なにか」があらわれている。
その「なにか」は、なんだろうか。
作者の脈動のような、確かな充足感のような__。
そして、それは、たしかにわたしたちの精神に流れ込み、わたしたち自身も躍動するのだ。