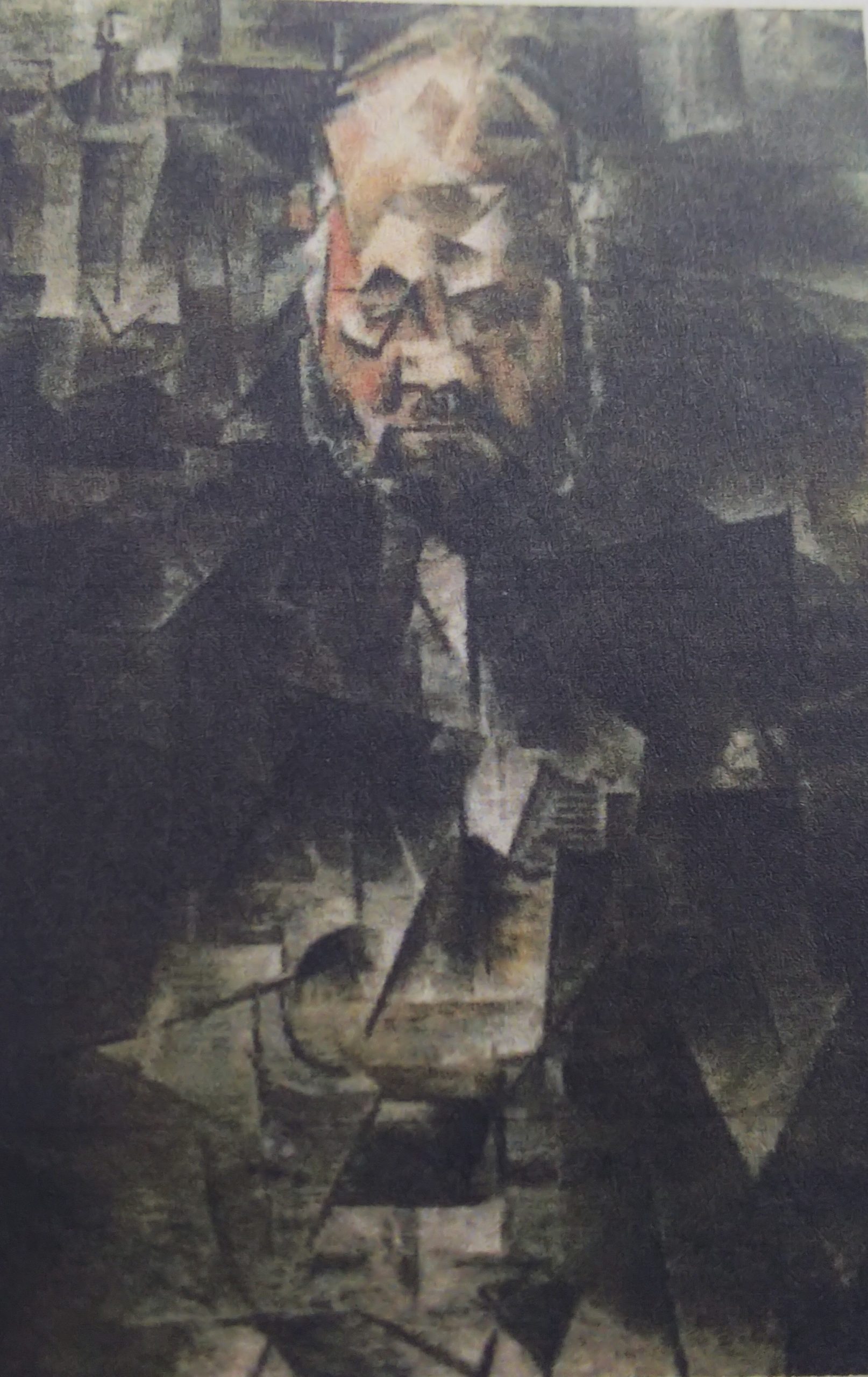失われた両腕の問題

高校生の頃、現代文の授業で清岡卓行さんの「ミロのヴィーナス」を読んだ。
ミロのヴィーナスを眺めながら、彼女がこんなにも魅惑的であるためには、両腕を失っていなければならなかったのだと、ぼくは、ふとふしぎな思いにとらわれたことがある。
清岡卓行「失われた両腕 ミロのヴィーナス」)
(
清岡さんはミロのヴィーナスに「両腕が無い」ことを賛美している。
完全体のままでは、想像しえない。
「ない」からこそ、
その先に続くかたちや、その両腕の行方を鑑賞者に想像させるのだとー。
そのときから、ミロのヴィーナスは気になっていて、学生時代にルーブルへ見に行った。
巨大な大理石の柱の林立する空間。
古代彫刻が左右に悠々と立ち並ぶなか、
その最奥の中心に彼女は輝いていたーー。

輝いていた、といってもそれは、
サモトラケのニケのような燦然とした輝きではなく、色に例えると、
そう、銀色。
なにか奥からじんわりただよってくる鈍い光を感じた。

けれど、その鈍い光は、静かでありながら、揺らぎなき歴史の重み、あらゆる文化の美をその身に凝縮したような、
なにものも太刀打ちできぬような衝撃をわたしに与えた。
なぜ、ミロのヴィーナスはこんなにも美しいのかーー。
私は、その答えを求めるように、そこでずっと眺めたのである。上から下から360度あらゆる角度から彼女を眺めたのである。

すると、どこからどう見ても均整の整った肢体。つやめかさの艶かしさ、そこに純真無垢な清廉さも宿している。ディティールの妙。。
わたしはこの時、清岡さんの言葉は頭のなかから消えていた。
腕がないから、美しいのか。腕があったらどうなのか。
そんなことを考える余裕もないほどに、角度を変えて彼女の姿を仰ぐたびに、
ただ、身の震える感動に打ち震えるだけであった。
完璧な芸術
この時、自分のなかでミロのヴィーナスは
「完全な美」として君臨したのである。
完全な美とはなんだろうか。
私は、そんなものは中々存在しえないと思っている。
どこかしらに綻びがあったり穴があいているものである。
けれど、ミロのヴィーナスは、本当に非の打ち所がないのである。
古代彫刻のなかでも、まったく格がちがう。
バランス、肉と骨の微妙な凸凹、体の軸は複雑に、ななめでも、真っ直ぐでも無い。
つやめかしく、アンニュイな、奥深い、身体のありさま。安定感と緊張感の同居ーー。

こんなものが、存在すること自体が不思議で仕方ない。
それは、古代人を崇拝するのに十分すぎるほどの圧倒的存在の事実であった。
私はこのとき、彼女の腕がどうなっているとか、まったく想像しなかったし、第一腕がないことにまったく注目しなかったのである。
ただその美にひれ伏した。
清岡さんはミロのヴィーナスは復元せずそのまま保存していたことを賞賛していたが、まったく同意である。
復元案などすべて空虚なものに思えた。
同時に、案が出ていたとしても、こんにちまで誰も彼女の姿に手を加えなかったことに心から安堵した。
しかし、一方で、わたしはある強い想いを抱いた。
それは、
彼女は「両腕」を失わなくてもよかったのではないか。
ということだった。
目が潰れていたり頭部が欠けたりしていてもいいし、あるいは腕があっても、同じように美しかったのではないか。
もしかすると、
体の欠損に関わらず、彼女は美しかったのではないか?
それでは、ここからその可能性を紐解いていきたい。
文脈や変化に左右されない美
美術作品は、しばしば歴史的、社会的文脈とは切り離せないものであり、例えば絵画であれば当時の社会情勢や宗教問題が絡んでいることが非常に多い。

しかし、時として
「もの自体がもつ存在感の強さ」のみで私たちに語り掛けてくる作品が存在する。
歴史的、社会的文脈を全て抜きにして、それ自体のもつチカラのある芸術。
それはわたしたちの想像力を超えてくる「なにか」であるーー。
そう、中世ヨーロッパの人々がローマの建築技術に驚愕し模倣を諦めたように。
また古代ローマの人々がギリシア彫刻を模倣したが、あくまで模倣であり、オリジナルの精緻には敵わなかったように。
そう、この世の中には
人間の創り上げたものなのに、
絶対に到達できないと思わせる創造物が存在する。
ナスカの地上絵しかり、ギザのピラミッドしかり、である。

ミロのヴィーナスはまさしくそのような芸術の象徴である。
彼女の美しさを例えるなら、そう。
ばっと天日干しされた洗いざらしのシャツのようなものである。

生地は丈夫で、コシがあり、しわや傷みも、生地そのものの良さのお陰で風合いとなって滲み出るーー。
多少、形や質が崩れても、
揺らがない根本の美。
あるいはそ崩れたさまがまた良いと言えるような味わい深さと言えば良いか。
その適当な扱いでも、十二分に美しい。そんなイメージだ。
この性質は、西洋の様々な美術や建築にもあらわれている。
石造の堅固な建築や彫刻は環境に左右されにくいし、
また、気候や風土も安定しており、豊かな土壌があり、自然災害も比較的少ない。
このような条件のなか、西洋の文化芸術は長い間崩れることなく今もなお、悠々と私たちの前に存在する。
日本の仏像は建築はこうはいかない。
京都奈良に代表される仏像や建築群はみなさんご存知の通り、木材が、ほとんどである。
火事がおこれば、燃え落ち、台風がくれば倒れる。
水に沈めば朽ちる。時が経てばひび割れ、劣化する。
もろく、壊れやすいのである。
だから、修復の職人や国の文化人のたゆまぬ努力によって守られているのだ。
こちらは例えるならアイロンでしわを伸ばし丁寧に手入れされたシルクのシャツのようなものである。
生地は強固ではなく繊細ですぐシワになるから丁寧に伸ばす必要があるー。
あらゆる繊細な扱いを必要とし、それでこそ保たれている美である。

さらに、仏像の美は仏像そのものの造形以上に歴史的文脈や宗教的文脈が重要になってくる。
なぜこの仏像がつくられたのか?
このポーズや表情はなにを意味するのか?
そういったものを理解してはじめて理解できる美が沢山ある。
もし、定朝の阿弥陀如来坐像※の右腕がかけていて、定印※2を結んでいなかったら、それは象徴性を欠く。
そう、「欠く」
のである。
左右対称の均等性や、手のさししめす意味が、仏像の美には重要であるためだ。

※阿弥陀如来坐像1053年 平等院鳳凰堂内 日本の古典彫刻におけるひとつの完成形として知られる傑作
※2:仏の示すハンドサインのひとつ。定印は悟りに入る意味をもつ。
そう、私たちは、仏像そのものではなく、
その裏にあるものや内包する仏の精神性に感じいるのである。
けれど、ミロのヴィーナスは__。
たとえ本来の意味がわからなくても、体の一部がけていてもびくともしない。
「欠く」という概念を置き去りにしたような、
歴史も社会も意味も超えて眼前に放たれた光のように存在するのだーー。

ミロのヴィーナスの失われた両腕は、清岡さんのいうように想像の翼となりうるかもしれない。
けれど、想像の翼がなくとも、私たちは感動できはしないだろうか。
視覚的な立体造形としての美しさ、インパクト。人間の身体、躍動への肉迫ーー。
ただ圧倒され、その存在にひれふすーー。それは、西洋文化における変化に左右されない堅固な性質を物語っているのだ。
優美で繊細な和の心
しかしながら、その主張だけでは私はここまで心動かされていなかったとおもう。
なぜ、ここまでミロのヴィーナスに惹かれるかーー。
それは、どことなく、彼女に東洋の、和の精神性が息づいているからに他ならない。
堂々とした主張のなかに光る控えめな一面__。
堅い大理石を豪快に、あるいは繊細に砕きあらわれた彼女は。
人間の肉体への賛歌だけではなく、仏静の心や奥ゆかしさを宿している気がしてならないのだ。

背中のなまめかしさのなかにある、「たおやかさ」をみてほしい。
腰下に巻き付く布の、肉感を繊細かつ動的にひろう流麗なしわの重なりを。

整った清廉な髪のまとまりと、ひそかに口角をあげ結ばれた唇を。
そのすべてが気品あふれる。
この絶妙なバランスこそが、彼女の存在をさらに神秘たらしめ、さらに親近感を覚える要因である。
古代ギリシアの文化、そう、アテネのポリスにも、東洋の和の精神に近いものが、息づいていたのかもしれない。
そう考えてゆくと、
彼女の美の親和性は、いよいよ遠い遠い時代と国を超える光となり、この身に降り注ぐのだー。